
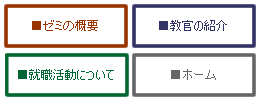
| <野生動物の生態観察入門 〜野外環境を理解するために〜> |
| 服部昭尚 (2000). In:(石上三雄編)「生物学フィールド学習」滋賀大学教育学部生物学教室.pp. 113-118. |
| 1. はじめに 野外環境の調査と言えば、「野外でサンプルを取ってきて研究室に持ち帰り、何らかの装置を用いて観察あるいは分析する」という研究方法が、今も日本では主流である。しかし、野外環境は、多様な生物から構成される一つのシステム(=生態系)であり、一部を取り出して持ち帰ったのでは理解できない側面ももつ。生物間の相互作用や動物(昆虫や鳥類など)の生息地の構造を、野外で詳しく観察することも忘れてはいけない。 現在、比較的よく行われている野外観察は、指標生物や種の多様性に着目した種数や種組成の調査である。しかし、このような調査だけでは、生物間のつながりが観察できないために不十分である。むしろ少数の動物に対象を絞ってその行動を観察し、動物間や動植物間の関わりを把握していく方が、野外環境の構造をマクロにとらえることができて有効であろう。動物たちの個性(種内の多様性)や生息地の多様性にも触れることができ、生物多様性の意味も実感できると思われる。 しかし動物の生態を野外で観察する手法は、一般的な生物学や化学などの手法と大きく異なるため、あるいはこれまでの学校教育で十分に扱われていないため、意外と習得がむずかしいようである。ここでは、比較的初心者にも観察しやすい水鳥の観察を例にしながら、野外観察に必要な基礎的事項を解説する。 |
| 2. 野外観察のための基本 i) 測定値の精度 科学の多くの分野では、より細かく、よりミクロにものごとを捉え、分析していこうとする傾向がある。測定機器の精度が向上し、精密な機器が扱えないと研究できない分野も多い。これに対して動物の生態学では、例えば、哺乳類のなわばりや行動圏を調査する時に、肉眼で目測さえ行うことがある。いい加減に思えるかもしれないが、要求される測定精度は研究対象によって異なるのがふつうであり、1〜2mの範囲なのか10〜20mの範囲なのかを問題とするような場合には、目測で距離を測っても大丈夫である。動物生態学では、精密な測定機器にたよらないために、かえって何のために何を測るのかをよく考えなければならない。 動物の群れサイズ(=群れを構成している個体の数)を測定する場合にも、やたらと正確に数えようとする人がいる。例えば、総数が134個体だったのか135個体だったのかにはほとんど意味はなく、100〜150の群れサイズであることがわかればよいことも多い。生態学では、しばしば観察値の対数変換を行うが、これは観察精度を感覚的に捉えるためにも有効である。すなわち、1〜10のレベルでは1個体づつ正確に数え、1000やそれ以上は桁数(オーダー)さえわかればよい、と言った感覚のことである。 ii) 景観の観察とフィールドマップの作成 野生動物の行動や生態を肉眼や双眼鏡などで観察する場合、対象とする種類にもよるが、フィールドの広さは、おそらく十数メートル四方から数百メートル四方の範囲となるだろう。まず市販されている2万5千分の一の地形図を購入し、この一部(もちろん調査場所)を何回か拡大コピーしながらA4〜B4くらいの白地図とする。これを調査場所に持ち込んで、土地形態や植物群落の位置と形、建物や丸太、大木など、目印となりそうなあらゆるものを書き込んでいって自分専用の地図を作成する。土地形態や植物群落など景観を構成している要素をよく観察すれば、いくつかの景観区分を設定できるであろう。例えば、琵琶湖の特定の湖岸であれば、ヨシ・マコモ群落か埋め立て湖岸か、河畔林は有るか無いか、湖岸線の形態は直線的かそうでないか、浮葉植物は有るか無いかなど質的なカテゴリーを設定して、その組み合わせによりいくつかの区分を定義することができる。 詳細な地図を作成するために、何度もフィールドに通って修正を重ねると、土地勘がつき、野生動物を観察する準備となる。できあがったフィールドマップを何枚もコピーしておき、これに対象とする動物の種類や行動様式、存在した場所などを克明に記録していく。 iii) 定点観察とセンサス 初心者が行いやすい野外観察の方法に、定点観察とセンサスがある。定点観察とは、観察地点をあらかじめ決めておき、そこから見える範囲を繰り返し観察する方法で、採食場所や繁殖場所などに焦点を定めた特定の行動観察に向いている。センサス(もともとの意味は人口概算のための訪問一斉調査)とは、一定の観察ルートを定めておき、決められた時間内にそこを歩きながら個体数や各個体の行動などを観察していく方法で、精度は落ちるが、広い範囲を対象にでき、野外環境をマクロな視点でとらえるのに特に適している。実際には、センサスを繰り返しながら、動物が多く集まる場所(採食場所や繁殖場所、休息場所など)を把握し、そこで定点観察も行うのが有効である。 定点観察とセンサスを組み合わせた観察ルールを、毎日のルーティン・ワークとして設定し、一定期間内は原則的に毎日それをこなすのがいい。しかし、場所によっては適切な道がなく、定点観察しかできないことも多い。 iv) 観察ルールの設定 基本的に、1回限りの野外観察では、何の結論も得られない。最低でも10回ほどは観察を繰り返し、統計的にデータが扱えるような配慮が必要である。このことも、サンプルを採集して分析するような研究スタイルと、かなり異なった点であろう。野外観察は、気象条件などさまざまな事柄に影響されてしまうため、基本的に結果の再現性が低く、統計的な扱いなしにはデータの価値は極めて低い。したがって、繰り返しの観察を、なるべく同じような条件下で行うために、「観察ルール」をあらかじめ明記しておく必要ある。例えば、「2週間ごとに(雨天は除く)、日没2時間前から日没までの間、瀬田川の河原の道を唐橋から北へ100mゆっくりと1時間かけて往復しながら、水鳥の存在場所と行動の観察を行った」、というように、観察者の方の行動パターンをあらかじめ具体的に決めておくのである。 v) 行動観察とパターン認識 とらえどころがなく、再現性がないように見える動物の行動も、しばらく観察をつづけていると、明らかな行動パターンとして認識できることが多い。例えば、水鳥の何種類かは、水面で逆立ちしながら水中の水草などを食べる。逆立ちしている間、いかにも水草を食べているような仕草を見せるが、残念ながら不明瞭なのでこの回数を数えることは難しい。しかし、水面で逆立ちをしている時間と逆立ちをした回数は正確に測定でき、したがって、どのような場所でその行動の頻度が高いのかを明らかにすることは可能である。この場合、逆立ち行動の頻度が高い場所が採食場所と考えられ、餌の詳細が不明であっても、水鳥にとってどのような環境が重要であるのかは研究できるのである(右下の写真を参照のこと)。  野生動物を観察すると、たいてい、その動物は餌を食べているか休んでいるか、移動中であることが多い。もっとも繁殖の季節だけは、求愛行動や巣作り、子育てなどの行動も頻繁に観察できる。はじめて観察を行う人は、動物が何もしていないのを見ると、がっかりして観察をやめてしまうケースがよくある。しかし、一見何もしていないように見える場合でも、次のような区別を考えてみよう。すなわち、1)補食活動:餌動物を待ち伏せている、2)休息:たまに毛づくろいなどしながら、食物の消化をしたり、休養をとっている、3)警戒活動:巣の周辺などで、捕食者やライバルの侵入を早期に発見するために警戒している、などである。これらの区別は、いわゆる文脈(コンテクスト)、すなわち前後関係や行動連鎖の観察により、容易に判別できることが多い。すなわち、「何もしていない」→「補食」なら1に該当するし、「何もしていない」→「追い払い」なら3に該当する。特に目立った行動が前後に見られないのであれば、2に該当するが、ふつう、毛づくろいや反芻行動などのさりげない行動をともなうことが多い。このように、何もしていないように見える場合でも、動物は何らかの目的のために、限りある時間を費やしていると考えられるのである。 動物の行動観察では、まず計測可能な行動パターンを見つけだし、その行動の単位時間当たりの回数や持続時間を測ることが基本と言えよう。尚、昆虫だけでも地球上に100万種以上いると言われる野生動物なので、ほとんどの種の行動パターンはあまりよく調べられていない。まずは教科書などに頼らないで、自分の目で行動パターンを記載してみよう。 vi) 動物の場所利用と生息地の構造 行動パターンの認識ができ、回数や持続時間の計測ができるようになれば、その行動を行った場所が有効な情報になる。精度の高い科学に親しんでいると、場所と言えば、X-Y座標上の点などを思い浮かべるかもしれない。しかし、ここではもっと大ざっぱに、河原の転石帯の上とか、水辺の湿った砂の上など、肉眼で識別可能な空間上の点を扱う。重要なことは、写真や現地訪問なので、観察者が違っても同じように識別が可能なカテゴリーを採用する点である。芝生と低木林の区別は誰にでもできることであるし、ヨシ群落と砂浜、転石帯もまた同様である。このような土地形態や植物群落に着目してフィールドマップを作成すれば、野生動物の場所利用に関する有益な情報源となる。 動物は、もちろん種類ごとに異なるが、広い環境の中から特定の場所を選んで利用している。例えば、カイツブリはヨシ群落の辺縁部に生息し、イワナは河川上流部の淵に生息する。動物が生活のために必要とする特定の場所のことを生息地と言うが、詳細な野外観察をつづけると、生息地を構成する細かい要素を明らかにできる。例えば、イワナは落下昆虫を利用するために、渓流に覆いかぶさるような深い河畔林を必要とし、強い流れに対抗しながらも運動量を減らすために、淵に沈んだ流木の陰を好む。このような、特定の動物の生態にもとづいた環境認識は、エコシステムの成り立ちを理解する際に有効である。 vii) 個体間相互作用の観察 一定の時間、ある個体の行動を観察していると、同種の他個体や他種の個体と何らかの相互作用を示す場合がある。例えば、なわばり行動を示す種の多くの個体は、自分のなわばりに侵入者があるとそれを追い払う。侵入者は、同種の場合もあるし他種の場合もある。いずれにせよ、どのような個体がどのような個体に対して、どのような行動を示したかを克明に記録する。「なわばり雄(大型個体)が、なわばりの周辺部で、侵入個体(同種の小型雄)に対して追い払い行動を示した」と言った具合である。大・中・小などの相対的サイズ・カテゴリーや、色彩変異の種類、雄と雌やオトナとコドモなど質的なカテゴリーを設定し、可能な限り詳細に記録するのである。また、「何もしなかった」という情報も重要である。例えば、なわばり雄が、同種の小型雄の侵入には無反応で、大型と中型雄の侵入には追い払い行動を示したとなれば、これは重要なデータである。要するに、刑事が容疑者の行動を詳細に観察・記録するような気持ちで、動物の行動を観察し、克明な記録を残すようにしよう。 viii) 個人による観察と安全性の確保 基本的に野生動物の生態観察は個人で行うことになる。これは、対象とする動物に対して「観察者によるプレッシャー」を少なくするためであり、自然なふるまいを観察したいからである。大学構内などで観察を行う場合でも、人の少ない休日の方が動物の観察には向いている。しかしながら、安全面を考慮すると、一人で出かけるのは望ましくない。したがって、2〜3人で出かけていって、別々の観察を行うのがよい。各自が自分の安全性に注意しながら自分の仕事を確実にこなし、かつ周辺にいる友人の仕事や安全性をも気にかけながら、いざという時は助け合うように準備をしておくのである。「基本的に人に頼らない、いざというときは助け合う」、これは野外観察にかぎらないが極めて重要なルールである。 |
| 3. 具体的な観察結果?野外観察で何がわかるのか? 本学大学院の修士論文(前智1997)を例にして、野生動物(この場合は水鳥)の野外観察でどのようなことがわかるのかを紹介する。ここでは、まず琵琶湖の松ノ木内湖での景観観察によりフィールドマップを作成し、その後2週間に1度づつ、定点観察を38回繰り返すことにより、水鳥の多様性を保つための環境要因が考察できることを示す。 i) 種数変動 このような調査の場合、一般的には種数の経時変化のグラフとしてまとめがちであるが、38回程度の定点観察では、ランダムに見える種数変動と渡り鳥の大まかな飛来季節などがわかるにすぎない。動物の生息状況の季節変化を知りたい場合には、2週間に1度程度の野外観察では、偶然によるばらつきが大きくてあまり役立たない。学校などでの野外観察が、昆虫などの出現季節に偏りがちなのは、他の方法論が普及していないためであろう。 ii) 生息地と種の多様性 38回の定点観察の結果を、観察場所の景観区分ごとに集計し、個体数・優占種順位のグラフにすると、どのような場所で多様性が高いかが明らかになる。もちろん、さらに3ヶ月程度の期間でくくって、季節性の点からまとめてもよい。 一般に、種類数が多く、各種の個体数にあまり差がないような時に多様性が高いと言い、種数が多くても特定の種が大発生しているような場合には、多様性が高いとは言わない。例えば、ある場所でランダムに1個体だけ水鳥を捕獲する場合を想像してみよう。多様性が低くければ、どんな種が捕獲できるかをだいたい言い当てられるが、多様性が高い時には予測不可能であろう。不確定性を扱った情報理論から開発されたShannon-Wienerの関数を利用すると、種の多様度を表すことが可能である。多様度指数(H’)は次のようになる。 H’ = -Σ (ni/N)log(ni/N) ここで、niは種iの個体数であり、Nは総個体数である。尚、情報理論では、log2(X)で計算された情報量をビットと呼び、log10(X)で計算されたものをディットと呼ぶ。生態学では、ふつう、自然対数の底を用いる。 ii) 優占種の場所利用と野外環境に関する考察 種数、個体数、景観区分の他に、行動のデータもとっておくと、情報量が多くなり、野外環境の構造と機能が考察しやすい。行動に注目すると、動物が、どのような場所で何を行っていたかが分析できるため、野生動物と環境との関係が機能的に把握できるのである。 この調査では、個体数が多かった優占種の3〜4種に注目し、どの景観区分で何をしていたかを集計すると、休息・採餌・遊泳など異なる行動をとる個体の割合が多い場所で、総個体数も多いことが明らかになった。言い換えれば、餌場と隠れ場所などが隣接している場所に水鳥の種類が多かったのである。一般に、水鳥の餌場は水深のごく浅い水辺であり(種類にもよるが、潜水できない水鳥はせいぜい数十センチの深さの餌しか食べられない)、隠れ場所はヨシやマコモ等の抽水植物群落であることが多い。陸地と水体がゆるやかに出会うごく浅い穏やかな水域は、抽水植物と沈水植物の異なる2つの植物群落を持ち、水鳥はこのような環境をうまく利用していたのである。このような野外研究から、埋め立てなどが水鳥に多大な影響を与え、エコシステムに変化をもたすこと等も明らかにできるだろう。 |
| 4. まとめ 種数や種組成、指標生物だけを観察するのではなく、景観区分や各種の個体数、さらには各個体の行動を観察すれば、野外環境をエコシステムとしてとらえるマクロな視点が養えると思う。ここではごく簡単に紹介したが、身近な野外環境で上記のような野外観察を行った例はまだまだ少ない。今後、具体的な研究例が増えていけば、多種多様な野外環境を理解する上での有効な情報が蓄積していくだろう。 |
| 5. 参考文献 粕谷英一・近雅博・細馬宏通(1990).「行動研究入門:動物行動の観察から解析まで」東海大学出版会 伊藤嘉昭・山村則男・嶋田正和(1992).「動物生態学」青樹書房 |
| ←卒業論文のテーマ |