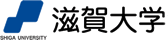研究主題
滋賀大学教育学部附属小学校 150周年記念研究「心豊かで実行力のある子供」育成のための認知・非認知能力統合的アプローチ1年次– 中動態的学びの過程における認知スキーマ:「実行力」の可視化 – |
研究の概要
本校は、150年の歴史の中で、常に時代の変化に対応しながら、子供[1]たちの成長を支えてきました。教育目標である「心豊かで実行力のある子供」の育成は、社会の変化に対応し、未来を切り拓く力を育むことを目指したものです。
2025年度は、本校創立150周年という大きな節目を迎えます。研究部として新たな研究を構想するにあたり、教育を取り巻く諸問題に目を向け、課題の特定を試みる中で、本校のこれまでと今、そしてこれからについて深く考える機会となりました。そして、本校の教育目標「心豊かで実行力のある子供」に目を向けると、解決すべき問題や達成すべき課題と重なり合っていることに気付かされました。
本研究は、滋賀大学教育学部附属小学校の教育目標である「心豊かで実行力のある子供」の育成を目指し、150年の歴史の中で培われた教育実践を基盤に、これからのAI時代を強く生きる子供たちを育むための教育方法を開発することを目的としています。
本研究は、変化の激しい現代社会において、子供たちが主体的に学び、豊かに成長していくための教育のあり方を追究します。特に、これまでの教育実践における課題を踏まえ、以下の3つの視点から研究を進めます。
| 1.子供たちが主体的に学び、自己変容を遂げる過程を多角的に捉え、「学びに向かう力」の成長軌跡を明確化する手法の開発
2.AI技術が進化する社会において、子供たち一人一人の経験や主観を尊重し、人間性を育む教育のあり方の検討 3.教師自身が学び続ける存在として、「子供たちの学びの実態に基づいた、そこでしかできない授業」の創造 |
本研究を通して、子供たちの可能性を最大限に引き出し、「心豊かで実行力のある子供」の育成に貢献することを目指します。
本研究の意義
教育において認知能力と非認知能力が重要であることは、多くの研究で指摘されています。しかし、これらの能力が実際の学習プロセスにおいてどのように相互作用し、学習者の成長に影響を与えるかについて、その詳細なメカニズムについては、依然として研究の余地が多く残されています。
本研究は、認知スキーマの変化を通して、認知能力と非認知能力がお互いに影響し合い、学習者がどのように伸びていくのか、その仕組みを明らかにすることを目指しています。先行研究では認知能力と非認知能力が個別に扱われることが多い中で、認知スキーマの変化を媒介とした両能力の相互作用を、動的[2]な学習プロセスの中で統合的に分析する点に、独自性があります。従来の認知的側面のみに焦点を当てた研究や、アンケート調査に偏重した研究では捉えきれなかった、学習者の成長過程における両能力の相互作用を、認知スキーマの変化を軸に具体的な授業実践を通して可視化します。特に、各教科固有の「鍵概念」と「教科独自のアプローチ」が認知スキーマの形成・変化をどのように促し、それを通じて学習者の認知能力と自己調整力や協働性などの非認知能力がどのように変容するのかを詳細に追跡することで、両能力の相乗効果を明らかにします。この研究は、実際の教育現場における学習者の成長を支援するための新たな知見を提供するものであり、教育実践への貢献が期待されます。
| 本研究のキーワード
・心豊かで実行力のある子供:本校の教育目標であり、研究全体のテーマ。 ・学びの中動態:学習者が、学ぶ内容や周りの人、環境などとの関わり合いの中で、思いがけない発見をしたり、考えが変わったりしながら、自らも変化していくような学びのあり方。 ・認知スキーマ:認知心理学における用語で、人が外界の情報を整理し、理解するための知識の枠組み。 ・認知・非認知能力の統合:本研究における学習者の成長を捉える上での重要な視点。 ・共創的学びのシナリオ:本研究1年次における授業設計の根幹をなす、認知能力の育成を主眼とした学びのプラン。 |
[1] 研究紀要内においては、子供たちの主体性を尊重する観点から、「子供」表記を原則とし、学校教育法上の「児童」を含む概念として用いる。ただし、「自立した学習者」における学習活動に焦点を当てる場合には「学習者」を使用している。
[2] 本研究における「動的」とは、学習者の思考プロセスを含む、広い意味合いを持つ言葉として使用している。したがって、「探究、発見、創造」といった、学習者の能動的な活動全般を指し、静的な内省や熟考も含まれる。