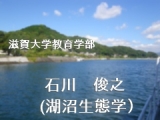お知らせ(古いもの)
- 2022年1月28日
- ○○のデジタル化という言葉をよく耳にしますが、研究で使うもの大半が、数値データである人間には何が新しいのかよくわかりません。データの取得から解析まで自動でアナログ手段の介在がないということなのかもしれませんが、機器には相当のお金がかかり、信頼性のチェックも必要であるという議論を超えてから現実になるものと思います。IT革命(イット革命)って覚えてる?
- 2021年12月21日
- 通勤手段の自転車を新調して一年余りたちました。体力がついたのか通勤時間はずいぶん短縮されました。帰宅時間が暗い時期に乗るので、安全グッズが充実し、そろそろエレクトリカルパレードに参加できそうなピカピカ状態です。自転車の楽しさを感じてきており、朝明るい時間はわざと遠回りするようになりました。「沼」に入り始めたかもしれません。
- 2021年12月10日
- 自己紹介のページのうち、自分の大きさや活性に関する数値を修正。対象生物のサイズや活性を測定することは、測定技術の進んだ生態学分野において、いまだに職人芸が残る(=小さな研究室でも輝ける)研究手段だと思います。体の曲がった甲殻類の長さを測るのが当研究室の常套手段です。(伸ばせ!写真とれ!)
- 2021年9月24日
- 先日、新型コロナワクチンの2回目の接種をしてきました。40代後半だと免疫力が高くないので副反応が低いのでは、とひそかに期待していましたが、喜ぶべきかしっかり38度台の熱が半日ほどでました。ワクチンではなく、本当に罹患したらあの38度が一週間前後続くかと思うとぞっとしました。気が付いたら接種か所が赤くなっていたので、これがモデル〇アームなのか、と思っていたら、家族からインフルエンザワクチンでもそれくらいは普通と言われました。ともあれ、10月から対面授業を行うのに気がかりが一つ減りました。(オンライン学会の発表直後に発熱開始でぎりぎりセーフでした。これは私のスケジュール調整のミスです。)
- 2021年3月4日
- "Think globaly, act locally"という言葉が環境分野で一世風靡したのはおよそ10年前だったでしょうか。この言葉には違和感を感じますし、自分の研究はこれまで全く逆の"Think locally, act globally"だったように感じます。そこで、google scholarで調べたところ、"Think locally, act globally"が117,000件、"Think globaly, act locally"は19,300件と10倍の差がありました。地球のことを考えて地域で動くのではなく、まず地域のことを考え、世界で動くというほうが研究対象としてより注目されていますね。身近な対象を大切にしましょう。
- 2021年1月14日
- センター試験対策としてオンライン授業を2週間しました。とても疲れます。やっていることは通常の授業と同じのはず(PowerPoint紙芝居の講談)なのですが、非言語コミュニケーションが使えないのでしゃべり続けないといけません。口下手な人間には苦行です。いかにいままで、授業中に苦笑いで間をつないでいたか理解しました。
- 2020年11月27日
- 数年前からはじめた自転車通勤を本格的に取り組んでいます。クロスバイクを購入したところ、通勤時間が3分の2になりました。寒い時期につらいだろうと思うかもしれませんが、汗が少し出る程度のこの時期は実はおすすめです。どうやらスポーツバイクを購入するにも良い時期(年モデルの在庫が適度にある)のようです。安全運転で。
- 2020年10月30日
- 少しの工夫で生活を充実させる「ライフハック」をこのコロナ禍で身に着けました。コーヒーを自分で入れる、安い、そこそこ美味しい、良い気分転換(気分転換のし過ぎ帽子も)。おやつはヨーグルトとバナナ(安い、快腸!)、ジュース替わりに酢ドリンク(安い、カロリー激減!)。もともと浪費はしないほうですが、今まで細かなところで浪費していたようです。次の目標はコ―ヒーを一杯20円を切ることです(まだインスタントコーヒーのコストに到達できません。200g400円を切っておいしい豆はあるのだろうか?)
- 2020年10月15日
- 大学や学術の在り方が世間で議論の対象になっています。根拠に基づいた客観的な議論が必要ですね。マスコミやインターネットでの発信でそれができているか、情報を得た人の「見抜く力」が問われていると思います。ところで、私は自分のいるキャンパスには、国旗掲揚する場所があるのか、全く知りません(体育館の中?)。※土日に国旗を掲げる人件費、物件費は用意されているのでしょうか?
- 2020年7月25日
- 今年度、「大学入門セミナー」という文献の調べ方やレポートの書き方を学ぶいわゆる初年次教育の科目を担当しました。オンライン授業で、「これがなかなか身につかない学生がいます。上級生になって再入門セミナーが必要です」と伝えたところ、授業の感想に「再入門セミナーを受けなくて済むようしっかり復習します」と書いた学生がいました。残念ながら再入門セミナーは開講未定です。自主的にやってもらえるとうれしいです。
- 2020年6月25日
- ようやく、きれいなお姉さんが宣伝しているRPGでゴールに到達しました。運動強度30、1日置きのプレイでした。途中で肉離れを起こし2週ほど休んだので、宣伝で言われている「連続3か月でゴール」とほぼ同じペースです。敵キャラであったトレーニンググッズが可愛らしく見えるのが、このエクササイズプログラムのポイントと感じました。ICTを使った教育の参考になります。(仕事に関連している・・・ということです。ヨガマットはいまだに嫌ですが・・・。)
- 2020年6月16日
- 遠隔講義の準備をしたり、WEB会議システムを使っていると、なぜかクシャミが出始めます。季節的に様々な草(イネ科植物)から花粉が飛んでいるものと思いますが、アレルギー反応を引き起こすのは、精神的なストレスも起因しているかもしれません。時々音声が乱れるのは、クシャミが出そうになってマイクを止めているからです(受講生の皆さん、理解をよろしくね。)
- 2020年5月21日
- 遠隔講義が始まって5週(一部の科目は8週目)立ちました。やはり準備にいろいろ工夫が必要ですね。この工夫を来年も使えればよいのですが、再開後にも対面授業を全くゼロにはできません。さて、準備した教材で授業するので、授業の時間は空いているだろうと思っていたのですが、PC画面を見ながら質問の対応や発言の応答をしています。※授業とは関係ない電話やメールに応答しています。対面授業で学生さんにダメといっていたはずなのですが・・・。
- 2020年4月22日
- 1か月前には想像もできないようほど、新型コロナウイルスが社会を変えています。世界中の大学教員が、遠隔講義の準備に追われています。すこしゲンナリするのは、こんな状況でも道具の「宗教戦争」が始まることです。20年前のapple派、Microsoft派の不毛な意地の張り合いから何も学べない人がいるようです。「ネズミをとるのが良い猫」という言葉を思い出しましょう。
- 2019年12月20日
- 今年は、久しぶりに体力づくりに勤しみ、なまったからだを鍛えなおすことができました。その結果半年で、体重が77kgから69kgまで絞ることができました。周囲からは過労だと思われていたようですが、実は毎日いい汗をかいていました。やったトレーニングは、きれいなお姉さんの指導によるボクササイズと、きれいなお姉さんが宣伝しているRPGです。RPGで一晩休むと体力が回復することの意味がよくわかりました。※鍛えた理由はハードなフィールドワークに備えてです。
- 2019年8月28日
- 普段はめったに船に酔わないのですが、本日は桟橋に係留した船で数時間VDT作業(ディスプレイを見ながら行う操作)をし、酔いました。係留をすると、船が揺れる動きのうちピッチ成分とロール成分がほぼ除去されます。残るのはヨー成分です。落ち?でしょうか。
- 2019年8月27日
- 主に一回生を対象にした湖上体験学習の全16回が無事に終了しました。8月前半には二回生対象の湖沼学実習も実施できました。協力してくれた上級生のみなさん、お疲れさまでした。
- 2019年6月19日
- 滋賀大学大津キャンパスに、気象観測装置を設置しました。データがインターネットを通じて閲覧できます。雨量計と風速計は準備中です。
- 2019年5月6日
- 当研究室で、教育学部・教育学研究科と6年間学んだWu QiganQian(う せいせい)さん(現、神戸大学大学院博士課程在籍)の論文がもう一つEnvironmental DNA誌に掲載されました。最新の技術として注目される環境DNAの専門誌の創刊号です。Wuさんが神戸大学進学後に取り組んだ内容です。北湖沖の調査で夏冬2回、長浜で合宿をしました。晩御飯後にひたすら湖北の味覚を楽しみました。
- 2019年4月11日
- 当研究室で、教育学部・教育学研究科と6年間学んだWu QiganQian(う せいせい)さん(現、神戸大学大学院博士課程在籍)の論文がアメリカ生態学会の学術誌に掲載されました。Wuさんの修士論文のデータをさらに丁寧に解析した結果をまとめたものです。雪の中湖北までスジエビをもらいに行ったのが随分前のことに感じます。
- 2019年4月2日
- 平成もあと1か月を切りました。人生の大半を平成で過ごした「平成たましい」もこれで終わりかと思うとしみじみします。ここ数年、大学生が平成生まれになり、21世紀生まれになり・・・。令和生まれの学生が入学するころ私は研究室の大掃除をしていると思います。
- 2019年2月26日
- 毎年恒例の花粉症シーズン到来。○○シーズン到来といってこれほど気分が落ち込むのは、花粉症のほかに何があるでしょうか。今年は風邪もひいてしまい何が何だかわからない涙声。
- 2019年1月16日
- 何度目かわかりませんが、「教育における三角関数の要・不要」が議論になっています。不思議なのは必要論に交流回路の基礎理論だとの意見が目立たないことです。そんな議論を交流回路の粋であるICT機器上で展開するのは、実に滑稽です。私は『「教養」の問題!』と一蹴したいところです。(交流回路を義務教育で習わないことの弊害も考えよう)
- 2019年1月4日
- 卒業論文の添削に忙しい時期ですが、体調には十分気をつけてください。私は年越しの風邪をひき、1月1日はほぼ1日中寝ていました。おかげ様で初夢がどれだかわからないくらいでした。始業の4日までにほぼ体調を戻したのは流石です(自画自賛)
- 2018年11月2日
- 東京ではハロウィンの騒ぎが話題のようです。ニュースを見ていて気になったのは、だれがお菓子を用意しているかです。いわゆる大人役。(つまり仮装は子ども役)
- 2018年10月23日
- この時期恒例の研究費の申請書の作成で、頭が混乱状態です。学生の皆さんは、この時期の教員の謎のハイテンションや、理解不能な集中状態は申請書作成のためだと諦めてください。
- 2018年9月18日
- 9月4日の台風21号によって琵琶湖の水が動いたというニュースがありました。この時,瀬田川の水位は40㎝程度下がったようですので,瀬田川の水が一瞬だけ逆流した可能性があります。桟橋の調査艇の係留ロープに南側からの強い力が加わった(一部破損)のですが,風の力に加えて逆流の影響があったかもしれません。
- 2018年7月25日
- 地震・豪雨の次は酷暑でした。2018年は試練の年かもしれません。酷暑といえばかき氷ですが,先日少し楽しいことを発見しました。ネットで話題の「豆乳パックをそのまま凍らせるアイス」を作り,かき氷器で削ると・・・。とてもおいしかったです。
- 2018年7月18日
- 地震・豪雨と災害続きですが,滋賀大学教育学部は幸いにも大きな影響はでませんした。琵琶湖では不思議な現象が起きたようなので,何とかデータ解析をしてみたいです。
- 2018年6月19日
- 大阪北部での地震で,滋賀大に通う学生さんにもいろいろな影響が出ているようです。震災に合われた地域の一日も早い復旧を願っています。
- 2018年4月20日
- 新学期が始まり3週間がたちました。毎年繰り返しのことが多いですが、一方で研究室は新しいメンバーになり新鮮さもやってきます。さてどんな一年になるでしょうか。
- 2018年2月8日
- 無事卒業論文発表会がおわりました。卒業論文では、生まれて初めてきちんとした形で研究をしたことと思います。研究成果はほんのわずかかもしれませんが、その小さな一歩が実は大きな一歩である、と説明できれば立派な研究です。
- 2018年1月16日
- 滋賀大学の通勤手当の規則に、交通用具は(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。という表現があります。同様の規定はいくつかの自治体などであります。原動機のついていない舟艇やそり、スキーで通勤するってすごいですね。そんな滋賀大学にはこれに対応して?桟橋があります。スキー・そり置き場も必用かも。
- 2018年1月4日
- 新年あけましておめでとうございます。昨年を振り返りつつ、今年の決意と行きたいところですが、毎年おなじことが繰り返されているのが現状でしょうか。昨年よかったことは、論文を読むのにタブレットを使いだしたらすごく便利だったことです。老眼対策ですね。今年の目標はたくさん論文をよんで、自分も論文を書く。結局毎年同じことです。
- 2017年4月20日
- 教育基本法第二条の五には「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに」という文言があります。博物館はまさにその役割の一翼を担い、それを支えているのが学芸員です。ところで、日本は法治国家であるとされ、政治家は法律をもとに国を動かすものだと思っていました。
- 2017年4月10日
- 新学期が始まってしまいました。今年度の担当授業を更新しました。
- 2017年2月2日
- とあるカプセル式のコーヒーメーカーを使っているのですが、カプセルを買うのが面倒で、普段はコーヒーメーカーでお湯を作ってインスタントコーヒーを飲んでいます。今朝、作ったインスタントコーヒーが抜群においしかったのですが、よくみると前日のカプセルが。新しい技を見つけてしまったかもしれません。失敗は成功の母
- 2017年1月13日
- 今年は新年のあいさつが遅くなりました。恒例の卒論・修論指導の時期です。今年は力作ぞろいといえるでしょう。やはり、自分たちでフィールドの観察結果をもとに計画した研究はうまくいきます。机上の議論しかない研究計画は考え直してください(これから卒論に取り組む学生へのメッセージ)。
- 2016年8月1日
- 定期試験も終わり、採点もなんとか終わりました。今年も夏本番の「湖沼学実習」を実施します。8月4・5日は観測、6・7日はキャンパス内でデータ解析と生物観察です。なお、今年から初等教育コースの2回生が受講生です。
- 2016年4月1日
- 2年連続の嬉しい4月1日。学生のみなさん、9月と12月に一週間ずつ研究のため不在にします。特に12月に不在の意味を理解するように!
- 2016年2月6日
- David Bowie の訃報につづき、Maurice Whiteの訃報とは。自分が学生時代から慣れ親しんだミュージシャンがいなくなるのは寂しいものです。
- 2016年1月7日
- まだ正月松の内なので、明けましておめでとうございます、と書けますね。さて、公文書に使うと問題になると話題の消えるボールペンですが、学生の論文の添削には赤色の消えるボールペンが便利だということに、昨年ようやく気が付きました。替え芯をたくさん用意して頑張るぞ!と思っていたのですが、赤ペンを入れる状態に達しない原稿が続出!!例年年末に赤ペンのインクが足りなくなってヒイヒイ言っているのですが・・・。
- 2015年12月1日
- 卒論の題目提出やゼミの中間発表が近づくと真剣になるのはわかりますが、次の日からスイッチが切れたようにふるまうのは褒められたものではありません。何かをやり過ごす練習をしているのであればそれは大学でやることではありません。社会にでれば幾度となく試練がやってきます。ただ、本当の意味で真剣になったことのない人には向き合えないような試練だと思いますよ。
- 2015年11月4日
- 昨日は文化の日でした。次男のリクエストで、伊賀まで忍者ショーを見に行きました。往路でみた渋滞を避けるために、帰路に国道422号で三重から滋賀入りを図るも、あまりの道の状態に唖然としました。これを酷道と表現するそうです。その夜、国道422号線は、我が大学の学生が毎日バスで通っている道そのものであることが判明し、一日二回も唖然としました。
- 2015年10月30日
- 写真をとるのが苦手な野外科学研究者は珍しいものかもしれません。本当に、いい写真を撮れたことはありませんし、撮ろうと努力するつもりもありません。いまだに、所属学部のページで私の写真が載っているのものびっくりですし、その写真がシンポジウムのチラシに使われているのを見ると卒倒します。
- 2015年10月20日
- 暇そうな「先生」ですら走り出す年末の忙しさ、ということで12月を師走というそうですが、現在ではとても失礼な話だと思います。これに従えば私たちは年中師走です。出雲大社の近くだけ「神有月」というように、局所的にでも名称は変えてほしいです。
- 2015年8月10日
- 気がつけば春学期が終わり、夏季集中講義の時期になっていました。今年度は「湖沼学実習」で琵琶湖の魚を捕まえて食べました。来年からは魚のおろし方を教えないといけない流れです。
- 2015年4月14日
- 世間では大学教員=時間に余裕があると誤解されていますが、少なくとも私の周りにはそのような教員はほとんどいません。一例を挙げると、昨日私はインスタントコーヒーを飲もうと朝8:30にコップに粉を入れたのですが、お湯を入れたのは夕方16:00というめまぐるしい一日でした。(さすがに極端な一日ですが)
- 2015年4月3日
- 京都と関西空港の間は99.8㎞のようです。残念ながら100㎞には届きません。
- 2015年4月1日
- 世間ではエイプリルフールの日ですが、4月1日はは大学などで研究する人には科学研究費補助金の内定が出る重要な日です。なんと今年は嬉しい知らせでした。ウソじゃないよね?
- 2015年3月16日
- 気がつけば新年でした。季節は花粉症まっただ中ですが、対策用メガネを新調したので、例年に比べマシです。昨年は3月に数回寝込みましたが、今のところゼロ。
- 2014年11月13日
- 先日、大学の近くの立木観音に学生と昇る機会がありました。800段近い階段は昇るのが結構大変ですが、20代の学生に負けずに昇れて一安心です。立木観音は厄除けでも有名ですが、おすすめポイントは新しくなったトイレです。とても風情のある建物です。
- 2014年9月30日
- 明日から授業再開です。一つでもよいので専門的なことを身に着けてみてください。そして、学生さんには、専門的ということの価値を理解して欲しいと思います。大学生と高校生との差はソコにあるはずです。
- 2014年7月22日
- 「湖上体験学習」が無事終わりました。今週木曜日の「環境教育概論」で事後指導がありますが、一息つきました。別の話題になりますが、教育学部の改組が予定されており、実習科目の実施体制などいろいろ準備が必要になりそうです。
- 2014年5月26日
- 今年も教育学部1回生全員を船に載せる「湖上体験学習」を実施しています。毎週のように琵琶湖にでると不思議なものがみえることがあります。5月18日は環水平アークを観察できました。写真をご覧ください。
- 2014年3月25日
- TVにつなげられる体重計を使ったところ、順調に体重が減りました。自分の専門分野からすると、「生物の体重が減ってしまうのは何か悪い条件があるのでは」となります。実は、順調に体重が減るのは毎晩のようにTVの前で運動をしているためです。これは、泳ぐのにエネルギーを使い果たし、なかなか大きくなれない魚のようなものです。(ちなみに、2か月で4㎏減りました)
- 2014年1月17日
- 実は、私にとって今年はいわゆる「厄年」です。科学者たるものそのようなものを盲信してはいけないのでしょうが、やっぱり気になるので大津では有名な立木観音に先日行きました。そこでおみくじを引いたはずなのに、くじの引換をしていないことに、その日の夜気づきました。「厄年」とは「忘却力」の増大がはじまることを意味しているのでしょうか。
- 2014年1月15日
- 今年もよろしくお願いします。新年なので、心機一転?とTVにつなげられる体重計を使うことにしました。体重や活動量の時系列データがグラフになると嬉しいのは生物を研究しているからでしょうか。
- 2013年12月10日
- 今シーズンの野外調査がほぼ終了しました。集中力をもって参加した学生さん、お疲れ様でした。ところで、40歳になって数週間、自分の成長に気づきました。1)なぜか白髪が減りました。鈍感力がついてストレスが減ったのでしょうか。2)船の運転時にミントタブレットをほとんど使わなくなりました。ひところは一日2パック使ってました。
- 2013年11月29日
- 昨日誕生日でした。40歳は孔子の言葉では不惑です。40年生きると板書の時に漢字が書けないことや言葉が出てこないことに動揺しなくなるのでしょうか。そんな境地に達したいです。先日は「フジツボ」が出てこず下手な絵を書いてごまかそうとして・・・ごまかせませんでした。
- 2013年10月30日
- 毎年恒例(トホホ)の科学研究費(通称・科研費)申請書の作成。トホホというのは、毎年書いているのは毎年敗退しているからです。締切間際に卒論を書くな!といいながら、指導している本人も締切間際です。なんとか締切には間に合いましたが、絵に描いた餅が餅にみえることを祈って・・・。
- 2013年10月7日
- お小言(9月27日)の続き。「やります」といってやらないのは、「やれません」「やりません」というより不味いことに早く気づきましょう。能力があることを誇示(だけ)することは、大人の社会では大した意味をもたないのです。(こういうことを言いだすのは年を取った証拠でしょうか・・・。)
- 2013年9月27日
- 来週から授業が始まります。ゼミも再開です。卒論提出までほぼ3か月だと気づいている学生は何人いるのでしょうか。「力を出す時には出す」というのが本当の意味での実力だと思います。最後に言い訳しないように!!
- 2013年8月19日
- 今年も8月の湖沼学実習を無事実施できました。受講生のみなさん、裏方で活躍したゼミ生のみなさん、お疲れ様でした。
- 2013年7月26日
- 学内のいたるところでセミの抜け殻を見つけます。写真に載せたように、セミにも人気のスポットがあるようですね。スマートフォンの画面を見ながら歩いていたら気づかないこと、いっぱいあります。学生さん、特に教員んを目指す人は「気づける人」になってください。
- 2013年5月21日
- 琵琶湖博物館でビワオオウズムシが初めて展示されます。少し前に実験のために短期間の飼育をしましたが、何もしなくても大丈夫と思いきや突然水槽内で全滅することがあり、結構手をやきました。
- 2013年 5月7日
- 私の担当している環境教育専攻は3年生からゼミに配属されます。最初は「お客さん顔」をしている学生さんばかりですが、4年生のゴールデンウィーク明けになると「お客さん顔」が消える学生が増えます。自分の研究は自分でスタートを切らなければ始まりませんよ。
- 2013年 4月16日
- 40年近く生きていて、いまだに勘違いをしていることが多いことに気づきます。先日、今までクリップファイルをバインダーと呼んでいたことに気づきました。正しくはリングファイル=バインダーです。間違えてしまったらどうすればいんだ。
- 2013年 4月8日
- 今日から新学期が始まりました。今年は生協の食堂が混むのはいつまででしょうか。20年前、私が学生のころはゴールデンウィークを超えればゆっくり食事ができるようになったものですが、今はだいぶ様子が違います。
- 2013年 4月1日
- 滋賀県は日本列島のやや西側にあるので温かいと誤解されがちですが、スタッドレスタイヤが必要な土地です。石山キャンパスではようやく桜が見ごろです。(東西で寒暖を気にするのは水循環的発想といえます)
- 2013年 3月22日
- よく学生さんから「授業の無い時は先生って何しているんですか?」と聞かれます。「研究」と答えられれば幸せなのですが、現実はそうもいきません。ふと本日送信したメールを数えたら30件でした。びっくり。
- 2013年2月13日
- 琵琶湖博物館でアナンデールヨコエビが初めて生体展示されます。低水温の水槽を維持するのは実はとてもたいへん。博物館の案内文の「底辺で支えている」が素敵。
- 2013年2月7日
- 卒業論文発表会がすべて無事に終了しました。病欠の学生のために原稿を代読するという珍しい場面もありましたが、それも含めて印象深い発表になったと思います。後輩によいプレッシャーをかけてくれて感謝します。
- 2013年 1月25日
- 来週から試験週間、つまり今週で今年の講義は終わりです。聴講してくれたみなさん、お疲れ様でした。今年度はあまり講義に工夫をする余裕がなく、少し申し訳なく思っています。
- 2013年 1月18日
- 4月からわくわく、どきどきした日々でしたね。時には長い中だるみもありましたが、いよいよ一年の集大成、フィナーレです。感慨ひとしおです。ふしぎの
- 2012年 12月25日
- こどもに人気の機関車トーマス。大人になってトーマスの話を見て感じるのは、社会の厳しさとそれに対してどう向かうかという寓話であったこと。ディーゼル機関車の黎明期、蒸気機関車へのリストラの嵐に対して蒸気機関車は時には失敗しながらも、仲間と協力し「自分たちでもできる」ことを示していくのでした。(できることを示そうとしない学生たちに日々悩んでいます。厳しい社会でやっていけるのかと。そもそも旅立つ先は厳しい世界であると知っているのかと。)
- 2012年 12月14日
- はやりの胃腸風邪にかかりました。おそらく下の子が保育園でもらってきたものです。幸い嘔吐も下痢もありませんでしたが、胃が痛くて食欲がわきません。辛いピークの日は午前中学生指導をした後、朝まで寝ていました。あとひと月後にこの状況だったら・・・・。留年する学生がでたかもしれません。免疫が切れないことを強く願います。
- 2012年 11月9日
- 最近特に思うのですが、仕事で頭がオーバーヒート気味の時、おいしいものを食べるととても落ち着きます。胃袋に血流が向かい、脳の興奮が抑えられるのでしょうか。特に、土日の混雑した琵琶湖で調査船を運転した後に感じます(学生のみなさん、グルメ逃避に付き合ってくれてありがとう)。
- 2012年 10月15日
- 学外からの琵琶湖観測体験乗船がひととおり終わりました。大きなアクシデントもなく一安心しました。
- 2012年 9月25日
- 夏期休業中にはいろいろなの野外観測を実施しています。ここ3日は連続で船の操縦をしてますが、大きなトラブルなく観測できました。学生のみなさんが手際よく観測機器を扱ってくれて感心しています。
- 2012年 8月16日
- 夏季集中授業「湖沼学実習」を、8月8日から12日の5日間で実施しました。暑い中集中力を持って臨んだ受講生、観測の実施・安全管理・データ解析に大活躍のゼミ生のみなさん、お疲れ様でした。
- 2012年 8月2日
- 昨年に引き続き滋賀大学の紹介冊子「滋賀大学案内」で当研究室が紹介されました。さらに、ゼミ所属の学生のインタビューや熱演写真も掲載されています。
- 2012年 7月26日
- 6月に怪我をしましたが、順調に回復しています。怪我は左手の指2本の骨折でした。昨日骨を固定していたワイヤーを抜き、ようやく水仕事に左手をつかえるようになります。
- 2012年 7月17日
- 教育学部必修の環境教育概論で実施している「湖上体験学習」が完了しました。3か月間、毎週のように琵琶湖の調査を実施しました。「担当授業」→「環境教育概論」とリンクをたどると調査結果の写真が閲覧できます(学部内限定)
- 2012年 6月3日
- 恥ずかしながら調査中に怪我をしました。日頃、安全に注意をするよう言っている立場なのに、面目ありません。学生のみなさんにはいつにも増して負担をかけますが、よろしくお願いします。
- 2012年 6月1日
- 天然真珠の写真を載せたらインターネットですぐ検索結果にでるようになりました。消すに消せないのでそのまま残しておきます。
- 2012年 5月25日
- 久しぶりの夜通しのプランクトンネット調査。手の皮の感覚は大学院時代以来です。
- 2012年 5月11日
- ”泥沼卒論”にならないか心配だった魚卵調査、なんとか卵を発見できました。
- 2012年 5月2日
- 環境教育概論「湖上体験学習」では観測結果を記録してます。学内限定で閲覧できます。上のリンクで担当授業→環境教育概論と選んでください。
- 2012年 4月12日
- 新年度の授業が始まり、あわただしい毎日です。新しい年度の試みとして、環境教育概論「湖上体験学習」を4月から7月に15班で実施します。季節によって変わる琵琶湖の姿に受講生は気づくでしょうか?
- 2012年 3月15日
- 新4回生3名と今津まで巡検。ザゼンソウ群生地を見学後、実習の宿泊施設の下見をしたのち、南下して和邇から近江舞子にかけての湖岸の様子を見てきました。どんな底生生物がいるか、採集してのお楽しみです。
- 2012年 2月12日
- 4回生の卒業論文発表会が2月10日に開催されました。その内容を初めて聴く人にむけてどう説明するか、これまでの学校生活で初めての経験だったと思いますが、なんとか目標は達成できたようです。
- 2012年 1月20日
- 4回生6人が卒業論文を提出しました。ひとまず、お疲れ様。次は2月の卒業論文発表会に向けて、「わかりやすさ」「説得力」を磨きましょう。
- 2012年 1月18日
- 2012年度ゼミ所属学生について記載しました。また、2011年度ゼミ生の名言集を記載しました(所属学生のページ)。食べ物の話が多いのは、フィールド科学系のゼミの特徴でしょうか?
- 2012年 1月16日
- 遅くなりましたが、今年もよろしくお願いします。卒論の締切が1月20日と迫り、ゼミ生はそれぞれ苦闘しているようです。教員は、口うるさい指導をしていますが、実は研究成果をみて楽しませてもらっています
- 2011年 11月8日
- 秋学期の講義資料を載せましたので必要な学生さんは利用してください。
- 2011年 11月5・6日
- 科学の祭典滋賀大会にゼミ生の杉山くんが出展しました。虫をじっくり観察するための工夫を感じてもらえたようです。
- 2011年 7月27日
- 春学期のゼミの最終回を、先週の台風による休講のために実施しました。4回生の卒論中間報告で、今年度最長のゼミ時間となりました。発表者、有意義な議論をしたみなさん、おつかれさまでした。2か月後に進展を報告してくれることを楽しみにしています。
-
- 2011年 5月26日
- 滋賀大学の紹介冊子「滋賀大学案内」で当研究室が紹介されました。少し照れくさいですが、うれしいですね。
- 2011年 5月8日
- 滋賀大構内で優占する外来植物 Phyllostachys heterocycla の駆除に協力しました。駆除後はもちろん有効活用!(5月15日にも駆除協力)
- 2011年 4月21日
- 予定表を追加。
- 2011年 4月5日
- 新学期です。進級・入学おめでとう。
- 2011年 2月7日
- 琵琶湖学特論定期試験問題(パスワードなし)。
- 2011年 1月14日
- 1月9日に今年初の琵琶湖観測をしました。
- 2011年 1月4日
- 本年もよろしくお願いします。
- 2010年11月28日
- ひとつ年をとりました。
- 2010年11月24日
- ウェブサイトを公開しました。