
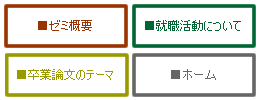
| <リンク> | |
| ◆これまでの研究の概要と遷移 これまで主に魚類を対象として、生物の社会システムと生息地の空間構造の関係をSCUBA潜水やスノーケル潜水による行動観察の手法を用いて研究してきました。いわゆるフィールド・ワーカーです。熱帯雨林などに生息する霊長類や鳥類の社会システムの研究をお手本に、水中を主なフィールドにしています。水中での観察の一番の利点は、空間内を自由に動き回れることです。森の中を自由に飛び回りなが生物の観察をしているようなものです。ある程度の距離を保ちながら静止して観察すると生物社会の一端を見ることができます。 この分野では、一般に、餌資源や配偶者をめぐる競争に注目して群れや縄張りの構造、雌雄の関係などを研究することが多いのですが、私は生物にとっての隠れ場所の数量や分布と社会システムの関係に興味をもっています。人間の世界のように明文化された法律のようなものが存在しないのにもかかわらず、生物の世界には予想外に洗練された社会システムが成立しています。例えば、人間以外の生物では、無益な闘争を繰り返して無秩序化することもありませんし、必要以上に搾取を続けることによって時間やエネルギーを浪費することもありません。競争を回避し、コストやリスクを抑えるために隠れ場所をうまく使っているようです。研究の目標は、攻撃的干渉の頻度を減らしたり、すみわけを促進するような生息空間の構造、すなわち隠れ場所の形態と社会システムの関係を,、フィールドでの観察から明らかにすることです。 |
|
| SCUBA潜水によって魚の観察ができるという愛媛大学理学部生物学科に進学し、3回生の終わり(1985年)から、イソギンチャクを隠れ場所や繁殖場所として用いるクマノミ類を生態研究のモデル生物(つまり、調査対象種)としてきました。クマノミ類とは、イソギンチャクとの共生で有名なサンゴ礁魚のことですが、26年後に総説論文として紹介することができました(服部 2011)。宇和海のフィールド近くに住み込み、猫と暮らしながら魚の研究に3年間(修士課程の終わりまで)没頭したことは、人生を大きく変えました。 研究の最初の段階では、隠れ場所(つまり、イソギンチャク)が豊富な場所(愛媛県愛南町の室手海岸)において、個体識別を施したクマノミの縄張り行動と配偶者の獲得行動を2年間追跡し、性転換のプロセスも継続的に観察しました(Hattori & Yanagisawa 1991)。その後、大阪市立大学の博士課程(動物社会学研究室)に進学し、隠れ場所が少ない場所(沖縄県本部町の瀬底島)において、同様にクマノミ類(→写真:この写真はカクレクマノミ)の社会システムと行動パターンを観察し、種内や種間で比較して論文としてまとめていきました。琉球大学熱帯生物圏研究センターがまだ全国共同利用施設ではない頃に、ここで3年間研究に没頭することができました。バブルの最盛期に最貧状態を経験することにはなってしまいましたが、生涯で一番充実した研究生活を送ることができました。 この結果、隠れ場所の分布様式は、予想に反して成魚の繁殖行動や配偶システムにはほとんど影響せず、むしろ縄張り行動と配偶者の獲得行動のパターンに大きく影響することがわかりました(Hattori 1991, Hattori1994)。つまり、各個体が採用する戦略は同じですが、具体的に採用する戦術は、他のライバルが採用する戦術の頻度に大きく影響されるため、隠れ場所の局所的な分布様式によって実際に観察される戦術が決まることがわかりました。具体的にはゲーム理論(進化的に安定な戦略モデル, 通称ESSモデル)を用いて予測し、観察データを使った検証を行いましました(Hattori & Yamamura 1995)。社会システム全体の様相は隠れ場所間の移動のしやすさによって決まっており、個体が採用する具体的な戦略(どのような状況でどのような戦術を採用するのかのルール)は本質的にどの個体でも同じであり、隠れ場所がどのように分布していても配偶者を獲得しやすいような戦略を採用していたことを示すことができました。 このような繁殖戦略の研究と平行して同じ隠れ場所を利用する2種の共存システムの研究も行いました。全く同じ種類のイソギンチャクを利用するクマノミ類2種の共存に、不連続な隠れ場所の分布と大きさの違いが不可欠であることも明らかにできました(Hattori 1995)。これらの研究成果により、卒論から8年もかかりましたが、1993年3月に大阪市立大学理学部(動物社会学研究室)にて博士号(理学博士)を取得できました。 |
 |
 |
学位取得後は、経済的な問題と研究テーマに伴う就職難の問題により、役に立たないクマノミ類の研究テーマを続けることはできなくなりました。途方に暮れましたが、研究によって身に付けたゲーム理論と適応戦略の理論を自分に当てはめて、研究場所を琵琶湖、研究対象を外来魚に変え、SCUBA潜水による行動観察の手法から環境問題にアプローチする研究を行うことにしました。大阪市住吉区から琵琶湖の大浦湾まで車で往復6時間、よく頑張ったものだと自分でも思います。この流れがプラスに働き、1年4ヶ月後に滋賀大学教育学部の環境教育湖沼実習センターというところに就職ができました。1995年8月のことです。 |
| クマノミ類以外のテーマでは、1991年に、シクリッド類の適応放散で有名な東アフリカのタンガニイカ湖の岩礁にて6ヶ月間、魚類の社会システムの研究にチャレンジしました。しかし、調査開始後にフィールドのあったザイール共和国(現コンゴ共和国)でクーデターが発生し、その後約一ヶ月間、隣国ブルンジ共和国に退避せざるを得なくなりました。しかし、ブルンジ共和国でも暴動が発生。第一次世界大戦時にドイツで建造されたという「リエンバ号」でタンガニイカ湖を南下し、タンザニア経由でザンビア共和国へ移住しました。貴重な経験はできましたが、肝心の研究の方はまとめきれておりません。しかし、この年、湾岸戦争やソ連の崩壊まであり、アフリカの歴史と生活、および西洋史などを勉強することができ、人生観は大きく変わりました。 大学院終了後の1994年より4年間、琵琶湖で潜水調査を行いました。琵琶湖に移入した外来魚の生態と生息地の構造に注目し、湖岸の地形の改変と沈水植物群落の立体構造、とブルーギルの場所利用との関係を研究しました。これまでに、急深になると生育深度の深いコカナダモが優占し、この種は在来種と異なって冬に枯れないため、水草帯を隠れ場所とするブルーギルには好適な生息地となることを明らかにしました。40年以上も前に米国より移入したブルーギルが、多様な湖岸形態を持つ琵琶湖にどのように適応しているのかも研究していましたが、外来魚駆除によってブルーギルが観察しにくくなり、その後、モーターボートの危険性や水草の刈り取り等の影響により、このテーマの研究はやめてしまいました。言い訳になりますが、モーターボートやジェットスキーの滑走は潜水浮上時には相当に恐ろしく、また、ルアーフィッシングの標的にされるのも意外と恐ろしいものです。まだ危険性の低かった時に、ブルーギルの調査とともに水草のデータを集めており、この水中植生の季節変化の観察は珍しいようでしたので、浅場の湖底の傾斜と水草植生の季節変化について研究成果を報告できました(Hattori 2004)。 1995年に滋賀大学に赴任後は潜水調査以外の研究テーマも模索してきました。これまで、琵琶湖の内湖の景観構造に着目して水域を区分し、水鳥の多様性と行動様式などの関係を学生とともに研究しました。この結果、水深数十センチメートル以下の極めて浅い水域と、特に周辺に人間が多く生息する場合、ヨシ帯などの遮蔽物が水鳥の多様性に影響していること等を明らかにできました(Hattori & Mae 2001)。その後、同様の手法を用いて景観構造と水鳥の多様性の研究を行っています。 1998年4月から、文部省の在外研究でオーストラリアのクイーンズランド大学に1年間留学し、亜熱帯河川の景観構造(河畔林や淵など自然の構造物の空間配置や微地形)と、レインボウフィッシュの場所利用を現地でのスノーケル観察により研究しました。一般に河川の魚類群集は、上流域では河畔林から供給される落下生物に依存し、中・下流域では付着藻や水草に依存しますが、レインボウフィッシュは中流域の水草帯に生息し、小型個体は表層で落下生物を、大型個体は底層の水草帯で水生生物を採餌するなど、中流域の景観構造に対応した採食戦略などが明らかになりました。特に小型個体は、日光を空中捕食者(カワセミ)の認知や体温上昇のために積極的に利用しながら水面採餌することを、モデル飛翔実験などにより確かめました(Hattori & Warburton 2003)。ワニでも出そうな亜熱帯の河川で潜水観察を行うのは正直ビビりましたが、その後、ワニはいないこともわかりました。フィールドまでは車で往復4時間、さすがに毎日は無理でしたが、いろいろあって楽しかったです。 |
|
 |
2001年3月から、もう20年以上も経ちましたが、空港問題で有名だった石垣島の白保サンゴ礁(←写真:黒っぽく見えるのがサンゴ群落、沖の白波までの部分がサンゴ礁)を新たなフィールドとしてきました。サンゴ礁の微地形とイソギンチャク類の分布様式、およびそこに生息するクマノミ類とさらにスズメダイ科魚類全体の社会システムの研究をしました。地形が複雑で自分がどこにいるのかさえもわからないため、高解像度航空写真(空中写真)の画像を地図として用いると、画像解析にって生息地の構造を広域的に抽出できることがわかりました。実際のフィールドで空撮画像の地図を用いてのクマノミ類やスズメダイ類等の分布と行動観察を重ね合わせると、社会システムの成立基盤を生態学的に分析できるわけです。 |
| |ゼミの概要|就職活動について|卒業論文のテーマ|ホーム| | |