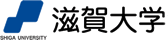まず、科学技術や情報通信技術の基礎を学びます。次に、それらが私たちの生活に深く浸透して利用されていることを理解した上で、健全な情報社会の発展や科学技術の進歩に寄与できる実践的能力をもつとともに、生活に必要な技術を身につけ、生活の中で工夫し創造する能力をもった子どもを育てるための理論と方法について学びます。さらに、初等・中等教育における情報科教育、メディア教育、技術科教育のリーダーとして、これら3分野の教育に関するカリキュラム開発や教材研究を行い、児童・生徒の実態に即した指導計画を作成して実践できる優れた教員の養成を目指します。
本専攻で学ぶ、情報と技術に関する広い知識、および、各種メディアを活用できる能力を応用して、e-Learningやインターネットを積極的に活用した学習環境の中で、文理融合の情報学、科学技術リテラシーに関する教育も推進します。
スタッフ紹介
岩井憲一(准教授:知能情報学・教育工学・音楽情報科学)
人間の情報処理過程をコンピュータ上で実現する。
岩井研究室では、知能情報学に基づいた研究を行っています。知能情報学とは、人間の情報処理過程を体系的にモデル化し、それをコンピュータ上でどう実現していくか(システム化)という内容に該当します。これまでに、教育・音楽などの各応用分野でシステムを構築していますが、Webサービスや知識ベースサービスといった知識処理関連研究など知能情報学そのものの研究についても行っています。
上記以外の分野・内容であっても、興味を持たれた方は一度ご相談下さい。
これまでの研究内容
- 指導案作成支援に関する研究
- 教師教育支援に関する研究
- e-Learning/WBLを利用した教育支援に関する研究
- 自動作曲・作曲支援システムに関する研究
- 知識ベースシステムに関する研究
- 構造化データに関する研究
岳野公人(教授:技術教育,環境教育)
ものづくりやプロジェクト企画・運営などを通した学習者の成長を心理学的な側面から分析する。
本研究室では、技術教育や環境教育における学習者の心理的側面について研究を行っています。学習の方法としてはものづくりの活動を取り入れています。特に,木材を扱うものづくりの場合には,森林環境からの恩恵としての木材と人間生活との関係性について,考える必要も出てきます。心理学的な側面では,作業中の集中状態,特に最適な経験と言われるフロー状態について研究を進めています。
これまでの研究内容
- ものづくり学習におけるフロー状態に関する研究
- 木材を利用した環境教育教材の開発
- ものづくり学習における学習者の意識構造の分析
- 落葉を利用した堆肥化の試み
右田正夫(教授:ロボット工学,認知科学)
ロボットのシミュレーションや製作にコンピュータを活用する。
私は、動物の行動や意思決定の過程をコンピュータ上で再現し、ロボットの制御に応用するための研究を行っています。研究室では、学生一人一人が個人的な興味や教育現場における必要性などの多様な研究動機に基づき、プログラミングやデータ解析などに幅広くコンピュータを活用した卒業研究を行っています。
卒業論文のテーマの例
- ロボットによる複雑ネットワーク上の経路学習
- 中学校技術科の教材としてのロボット製作
- プログラミング学習におけるロボット利用の効果
水上善博(教授:情報・量子に関する技術)
コンピュータシミュレーション
近年の情報技術の進歩に伴って、コンピュータシミュレーションは、現象を予測するための強力なツールとなりました。本研究室ではコンピュータシミュレーションを用いて様々な現象の解析を行っています。具体的には、コンピュータ計算による物質の性質の予測や今後の発展が期待される量子コンピュータの基礎となる量子に関する技術の開発などです。
これまでの研究内容
- ダイオキシンの毒性に関する理論的研究
- 新型コロナウイルスの抗ウイルス薬に関する理論的研究
- 量子力学における昇降演算子の研究